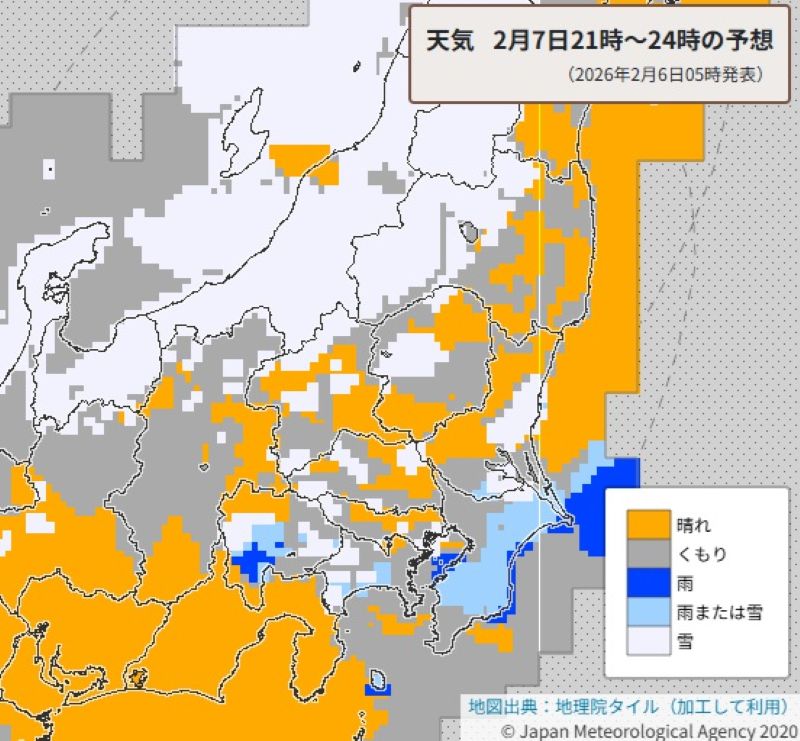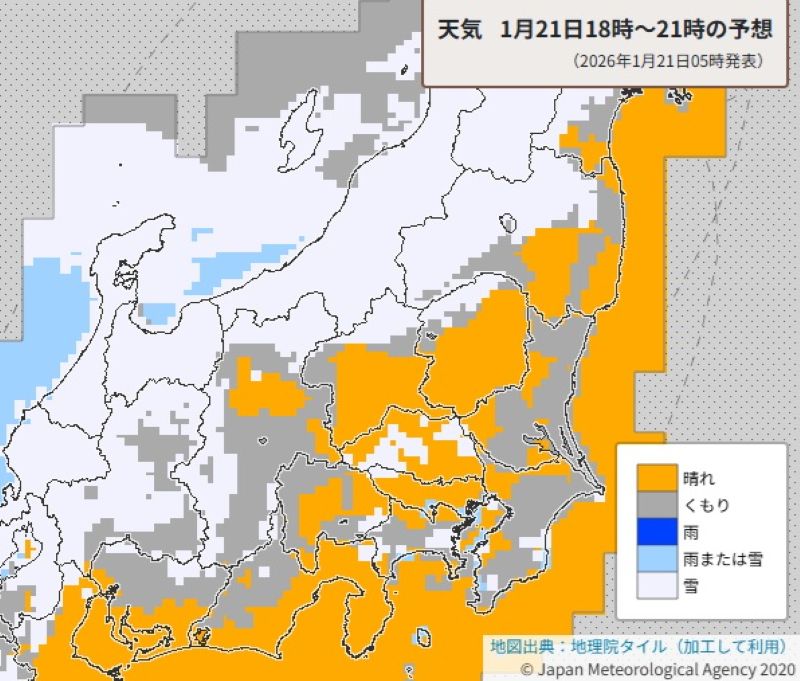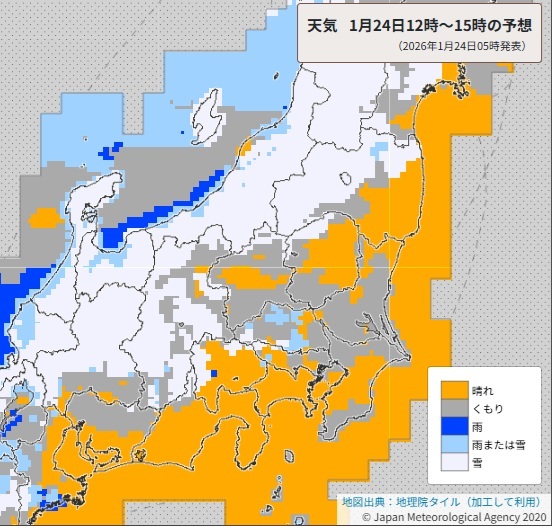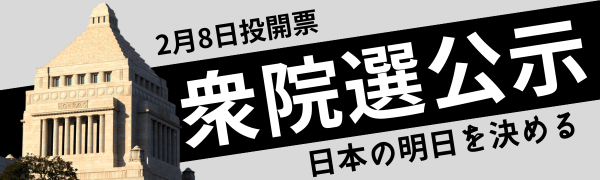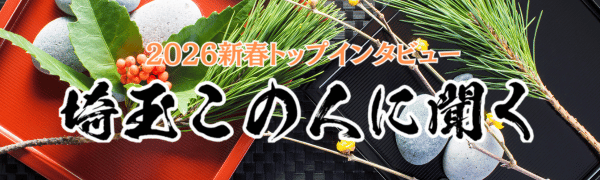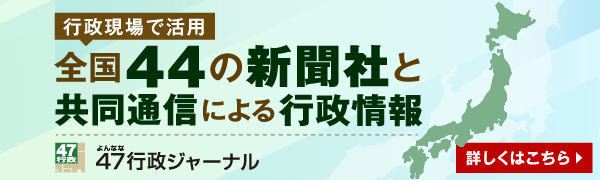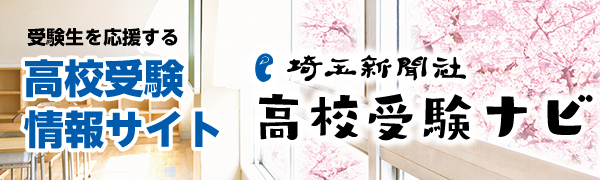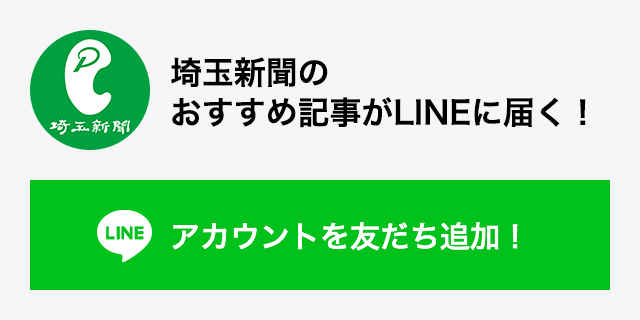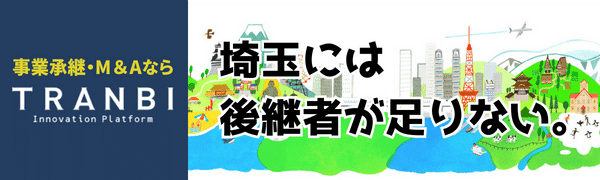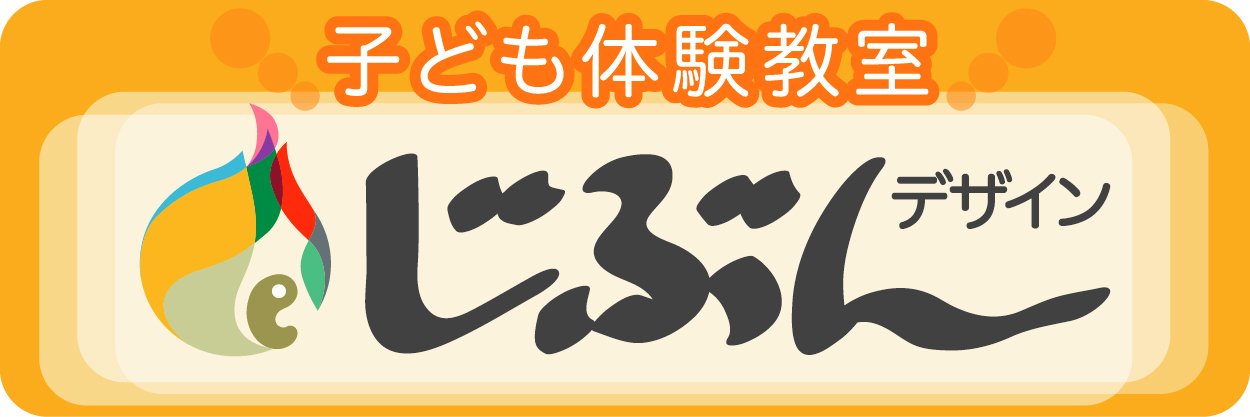埼玉で1位…移住相談件数、3年連続でトップ 移住者を引きつける小川町 キーワードは「農ある暮らし」
首都圏への一極集中と地方の人口減が進む中で、注目されているのが地方への移住だ。小川町は、県内の市町村別の移住相談件数が3年連続でトップ。移住者を引きつける魅力は何なのか。キーワードは「農ある暮らし」だ。
■有機農業の先進地
2021年秋に横浜市から小川町へ移住した会社員の釜井昌二さん(52)。移住の切っかけは滑川町の事業所への転勤だった。「どうせなら田舎暮らしでも」と、軽い気持ちだったという。
会社員の家庭で育ち、農業とは縁がなかったが、小川町の有機農業に関心があった。移住の相談窓口となった移住サポートセンターの勧めで、小川町有機農業入門講座を受講することになった。
小川町では1970年代から有機農業が営まれている。その開拓者が故・金子美登さんだ。その教えを受けた人たちが独立し、町内全域に有機農業が広がった。今では県内でも有数の有機農業が盛んな地域となっている。
講座は町内の有機農家が講師となって、1年間にわたって有機農業の基本技術を学ぶ。循環型農業で、里山の四季や風土に合わせて少量多品種の作物を育てる。「こんなすごい農業をやっている所に、うっかり来ちゃった。喜びと驚きと衝撃を受けた」と振り返る。
■畑で循環型社会を
講座修了後は、町内に小さな畑を借りて自家消費用の作物を育てている。現在栽培しているのはダイコン、ナス、トマト、シソから、バケツで育てている水稲まで約20種類。
化学肥料は一切使わず、町内で給食の残りかすから作られている液肥を購入して使用している。また、自宅で出た生ごみをホーローの器に入れた後、微生物の力で土に返し、肥料として畑にまいている。残ったプラスチックごみはスーパーの回収ボックスへ。日々の生活で、ごみはほとんど出ないという。「この小さな畑で循環型社会がつくれないか、チャレンジして生活している」と話す。
農作業は会社から帰って1時間ほどを当てている。畑仕事をしていると、仕事の疲れも吹き飛ぶという。「土の中にいる微生物が(疲れを)エネルギーや、やる気に変えてくれるんじゃないですかね」
■自然の中で生きる
こうした生活は、横浜にいた時は考えたこともなかったという。都市の生活は便利で物があふれている。「お金がいっぱいあったり、欲しいものに満たされていたり。でも、そうしたものは言い出せばきりがない」と話す。
小川町では、時に有機農業のアドバイスをくれる農家をはじめ、多くの人と友人になったという。「この人たちがいる、この自然の中で生きることが、自分にとっての豊かさ。人それぞれ価値観が違うので、強制するつもりはないですが」とほほ笑んだ。
7月12日に釜井さんの小川暮らしの「お話会」と、自家栽培の野菜を使ったランチ交流会が行われる。申し込みは、小川町移住サポートセンター(電話0493・53・6717=平日午前9時~午後6時)へ。
◇
■“東京に近い田舎”で人気
県地域政策課によると、2023年度の市町村別の移住相談件数は小川町が766件でトップ。2位の秩父市(398件)、3位の飯能市(369件)と比べても、その人気ぶりは際立っている。しかも、集計を始めた21年度から3年連続の首位だ。
背景にあるのは、町の移住への取り組みだ。都内などへの通勤者を対象に東武東上線の座席指定券の補助、空き家バンクや空き家改修費の補助などを実施。小川町駅前には、NPO法人霜里学校が町から運営業務を委託されている移住サポートセンターがあり、移住希望者の窓口になっている。
同法人によると、24年度で同センターに相談して移住が決まった件数は54件。同センターを通していない人もいるため、実数はもっと多いという。
同理事の八田さと子さんによると、小川町が選ばれる理由は、町の施策の他、東京まで電車で1時間という立地でありながら、里山の魅力が味わえることにあるという。「田舎暮らしがしたいという人には『畑をやりたい。できるならば有機で』という人が多い。そこで、地域的に有機農業をやっている小川町が選ばれているのではないか」と話していた。