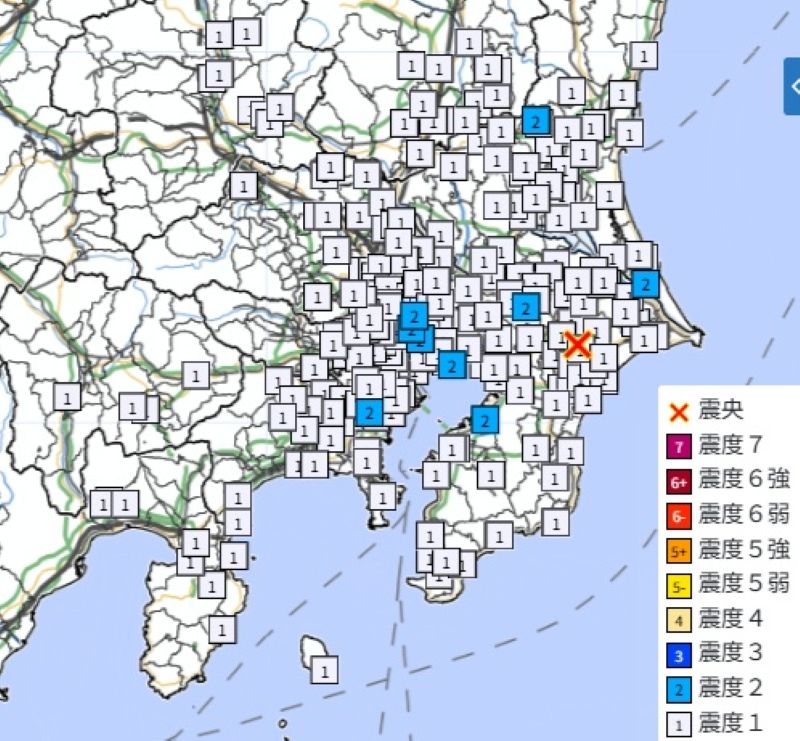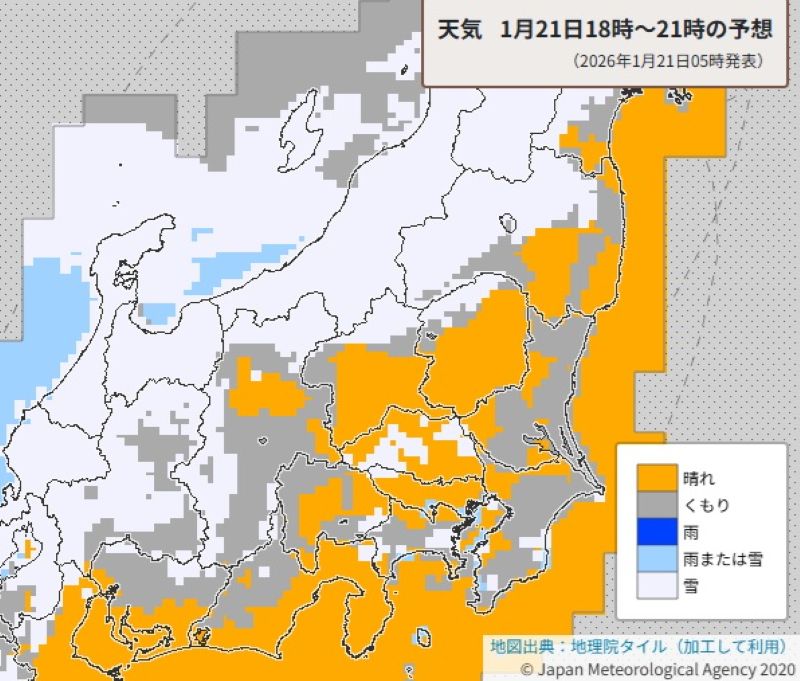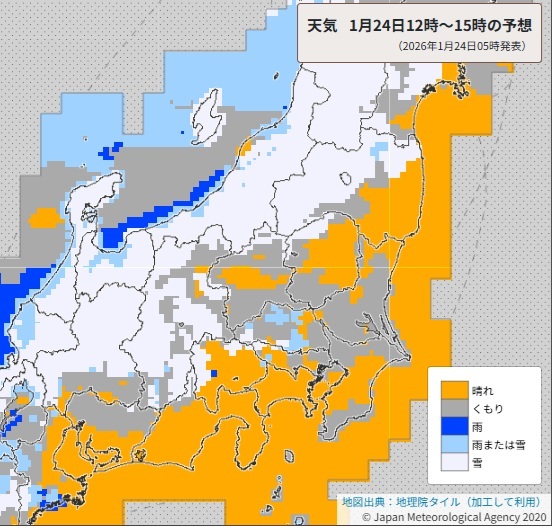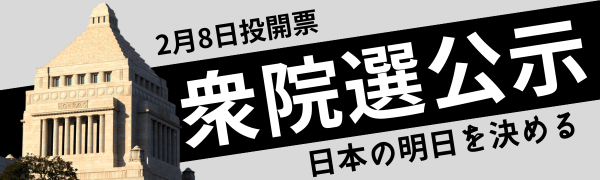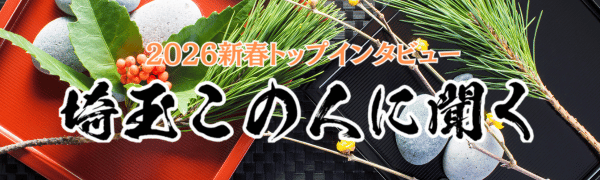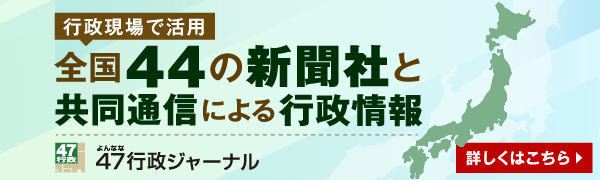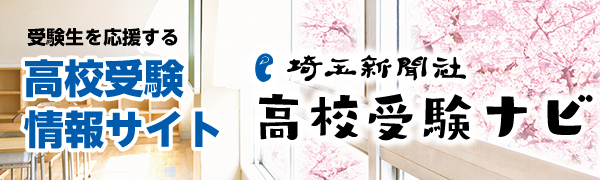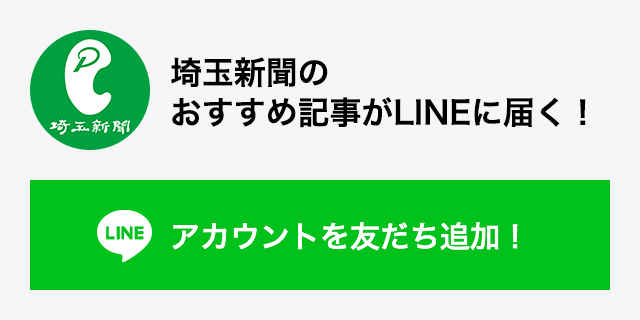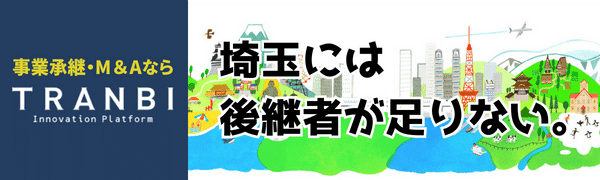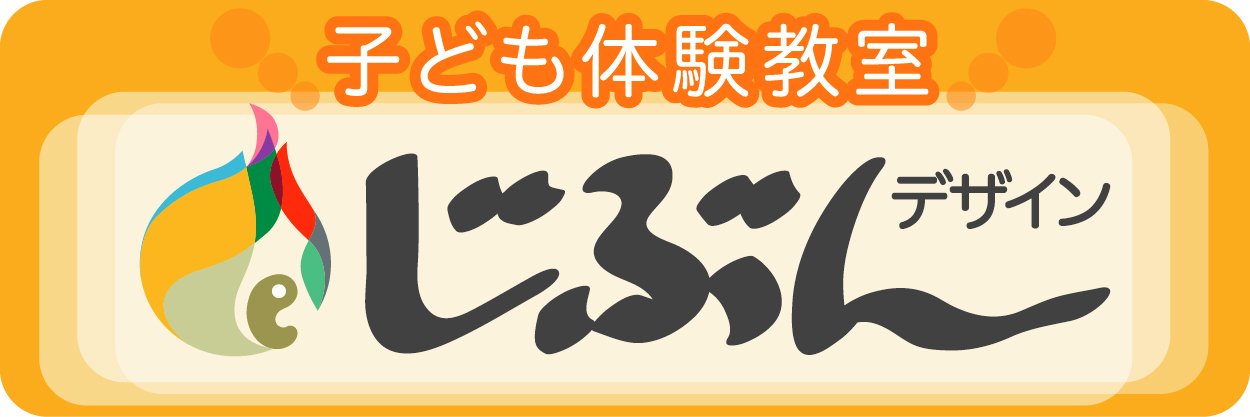ミツバチの力を借り、緑を増やす取り組み 春日部夢の森公園、県民協働の養蜂部が発足 植物の受粉を促す益虫、甘くて栄養たっぷりのハチミツ作る…園内のイベントで販売の予定も
甘くて栄養たっぷりのハチミツを作るミツバチ。植物の受粉を促す益虫の力を借り、緑を増やす取り組みが、春日部市下大増新田の県営春日部夢の森公園で始まった。県民協働の公園づくりの一環として今春、養蜂部が発足。部員たちは、家族のため懸命に働くミツバチの成長を見守り、彼らが安心して暮らせる豊かな自然環境の実現を目指している。
■小さな大家族
5月22日、公園の一角にある養蜂場で、防護服に身を包んだ部員たちが、巣箱を開けて巣の状態を確認していた。女王バチは無事か、産卵しているか、子どもたちは順調に育っているか。巣が手狭になると、引っ越しの「分蜂」が起きる可能性もある。スズメバチやカマキリといった天敵にも警戒が必要だ。
ミツバチは1匹の女王バチを中心に、世話をする大勢の働きバチと交尾を担う雄バチで群れを構成する。五つの巣箱にはそれぞれ1万~4万匹の「大家族」が生活。毎日2千もの新たな命が誕生し、多くの植物が開花するこの時期は特に活発になる。ブンブンと頭上を飛び回る羽音も大きい。
「生き物と自然が相手なので先が読めず、教科書通りには進まない。これから暑くなると作業も大変になってくるが、小さなミツバチたちが力を合わせ、長い時間かけてハチミツを作り上げていることを知ってもらえたら」。養蜂部を指導する地元の養蜂家田中麻実さん(40)は語る。
■人と自然の調和
広さ約14ヘクタールの公園は2021年、「都市部における緑の再生」を目標に掲げてオープンした。多様な生物が暮らす憩いの場を、県民と協働でつくり上げていくのがコンセプト。植樹や花壇づくりなどが進められる中、シロツメクサなどの蜜源が豊富な環境を生かし、新たに養蜂部が発足した。
部員は公募で集まった男女12人。「ミツバチの日」の3月8日に始動し、木曜日の午前中に活動している。春日部市のセラピスト前島まりさん(51)は趣味のガーデニングを通じて養蜂に興味を持った。「一生懸命、卵を産んだり、蜜を集めてくる姿にいとおしさを感じる。ミツバチのためにも、花を育てようという気持ちが芽生えた」
「役割分担して、群れ全体が一つの生き物のように行動するのがすごい。生まれた時はみんな同じ姿なのに」と社会性昆虫の生態に驚くのは、春日部市のイタリア語講師向井順子さん(51)。養蜂を始めてから「ほかの虫のことも気になり、目を向けるようになった」という。
■食糧生産に貢献
ミツバチは「絶滅したら4年後には人類も滅びているだろう」と言われるほど、食糧生産で重要な役割を果たしている。11年の国連環境計画(UNEP)報告書によると、世界の食糧の90%を占める100種類の作物のうち、ミツバチが受粉を媒介しているのは70種以上。北半球を中心に激減しているミツバチを保護しなければ、食糧不足のリスクが高まると警告している。
養蜂部では採取したハチミツを部員たちで分け合うほか、余った分は園内のイベントで販売する予定だ。緑を増やしながら、ミツバチが人間の生活に欠かせない存在であることもアピールする。田中さんは「ミツバチが当たり前に暮らす地域。そんな豊かな自然環境を春日部夢の森公園から広げていきたい」と話した。