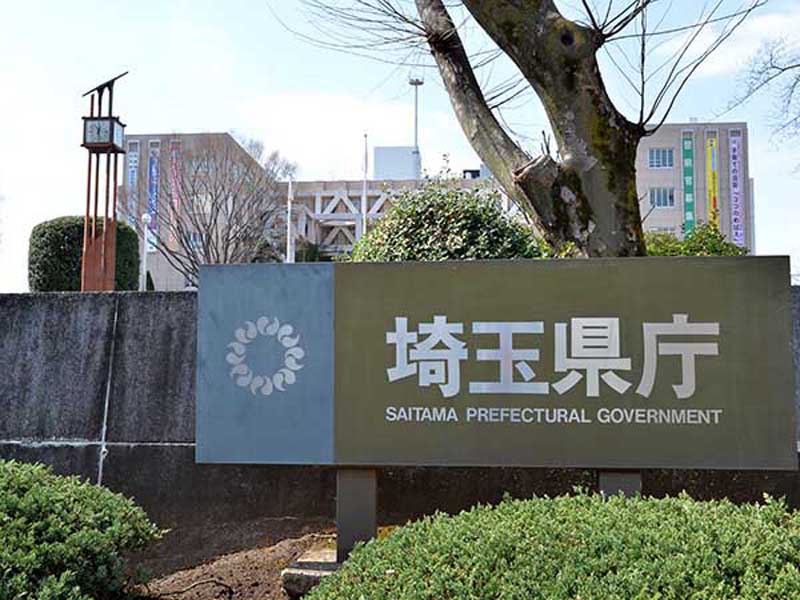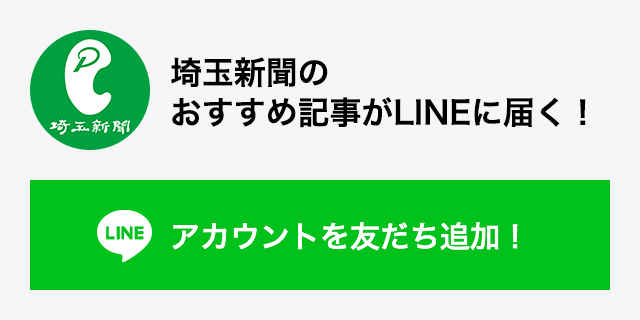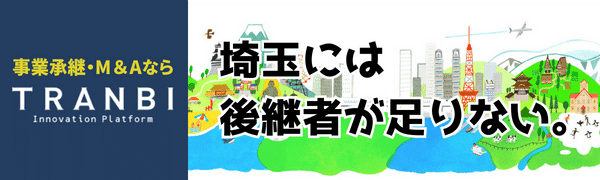【逍遥の記(21)】今を生きる人を触発できているか? 開館以来初の現代美術展、国立西洋美術館
東京・上野の国立西洋美術館にはめったに行かない。昔の西洋絵画や彫刻を見るのは好きだが、作品の“過剰さ”と人混みに辟易するからだ。よく足を運ぶのは現代美術の展覧会や芸術祭で、会場をゆっくりと回りながらあれこれと考える。自分の無意識や先入観を突かれてはっとしたり、問題意識を深めたり、笑い出したり。触発されるような経験が必ずあって、行って良かったと思う。同時代を生きるアーティストが、この時代を、この世界を、どう見て、どう切り取っているのか。それを知りたくていそいそと出かける。
だから、今回の国立西洋美術館の試みにはそそられた。タイトルは非常に長い。
「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問-現代美術家たちへの問いかけ」(~5月12日)。1959年の開館以来、初となる現代美術展だという。
3月11日の記者内覧会の際に、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの侵攻を巡る抗議行動があったと後で聞き、余計に「見に行かなければ」と思った。4月中旬の平日、会場に向かった。
■倒される彫刻
オーギュスト・ロダンの彫刻「考える人」と「青銅時代」が床に転がっていた。見た瞬間、小さな衝撃を受ける。これは何を表現しているのだろう。小田原のどかの新作インスタレーションは、2章「日本に『西洋美術館』があることをどう考えるか?」にあった。
ロダンの「考える人」は日本で最も知名度が高い美術作品の一つではないだろうか。それには、国立西洋美術館の存在が大きく寄与している。そんな西洋彫刻の代名詞のような作品が、台座から外されていま、床にある。
頭をよぎったのは、人種差別に抗議する「ブラック・ライブズ・マター」運動の中で彫像作品が次々に引き倒されていった映像だった。価値観を揺るがされ、権威が失墜するとき、彫像が転がされる。日本では、北海道の開拓記念碑として制作された「風雪の群像」がアイヌ民族への差別であると批判されるなか、「東アジア反日武装戦線」に爆破されるという事件が1972年に起きた。このことは、小田原作品の展示説明に記されていたことで思い出したのだが……。
彫刻作品が転がっていることでもう一つ想起したのは、地震や津波といった災厄のことだ。災害の多い日本では、美術館も常に対策を考えているだろう。長い時間の経過による劣化にも耐える必要がある。美術館に課せられた困難な課題をも、示しているような気がした。
小田原のインスタレーションを見ていくと、「転倒」と「転向」を重ね合わせて考えていることが分かる。そして、そのどちらも、必ずしも悪い面ばかりではないという思想も伝わってくる。中でも、水平社宣言の起草者で、獄中で転向したとされる美術家、西光万吉を紹介する展示を興味深く読み、彼の絵画作品「毀釈」に見入った。そこには、皮肉めいた笑顔を浮かべる老僧が描かれていた。
■無意識の排除
3章「この美術館の可視/不可視のフレームはなにか?」では、田中功起が美術館に対して提案するという枠組みの作品に意表を突かれた。最初の提案「作品を展示する位置を車椅子/子ども目線にする」という文章が、まさに車椅子や子どもが見やすい低い位置に掲示されている。視線を落としたり、しゃがみ込んだりしてそれを読み、これまでずっと多数派の人間として作品を見ていたことを思い知らされる。
「乳幼児向けの託児室を設ける」「翻訳言語の選択を拡張する」といった提案にいちいちうなずき、「日本の美術館で使用される翻訳言語にクルド語が選ばれたことはあるだろうか」という問いかけにうなる。市民に開かれた公共空間であるはずの美術館は、一体誰を「市民」と想定し、誰を無意識に排除しているのか。それが、うっすらと浮かび上がってくる。
そして、田中の作品と同じくらいか、それ以上に、この美術館の在り方を力強く問うたのは、弓指寛治の作品ではないだろうか。それは、4章と5章の間の「反─幕間劇──上野公園、この矛盾に充ちた場所:上野から山谷へ/山谷から上野へ」というセクションに並んでいた。
■視野を広げる
国立西洋美術館がある上野公園には、少なからぬ路上生活者がいる。弓指はまず山谷に通い、上野公園にも行くようになった。そこで暮らす人たちへの炊き出しやドヤ巡り、食事の配膳などの支援に参加し、雑談や聞き取りをした。山谷には約1年、通ったという。
その上で描かれた色彩豊かな絵を見ながら、聞き取った内容を記録した文章を読む。絵と文章を組み合わせた絵本のような展示と向き合うと、だんだんと登場人物たちが身近な存在に思えてくる。そこには声高な主張ではなく、一人一人のささやかだが確固とした生があった。
この展示は、本展企画者で主任研究員の新藤淳の提案を弓指が受ける形で実現したという。美術館は誰に開かれているのかという田中の問いが重なってくる。
「山狩り」という言葉がある。皇族がこの美術館に来るときなどに、路上生活者を強制的に退去させることを指す。彼らから西洋美術館はどう見えるのか。弓指の作品は、その存在を揺さぶる視線を美術館に注ぐ。
本展冒頭に示されている問いは、ここ国立西洋美術館が現代のアーティストを刺激し、未来の芸術を育む場となっているか、ということだった。アーティストたちはその問いの視野を広げ、もっと深いところまで連れて行ってくれたように思う。(敬称略/田村文共同通信記者)