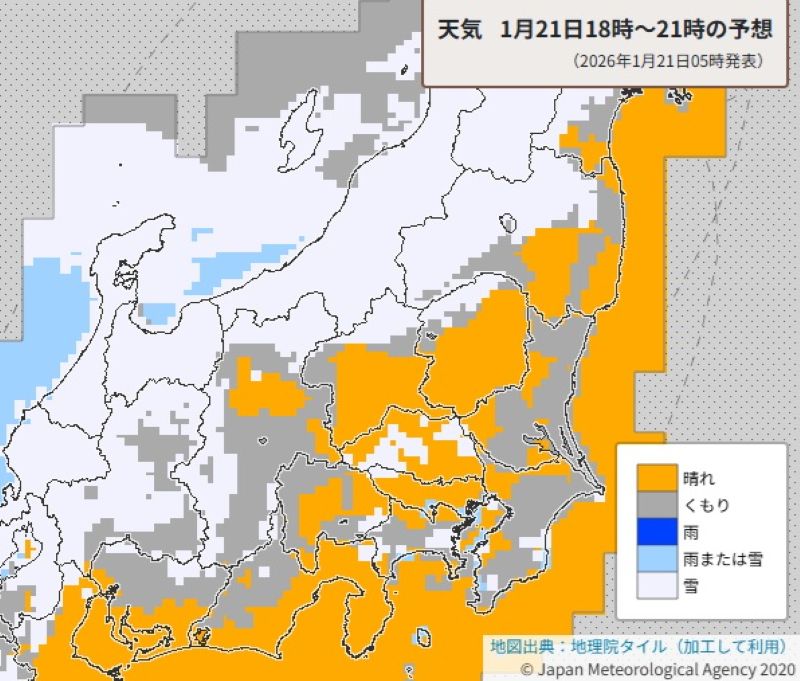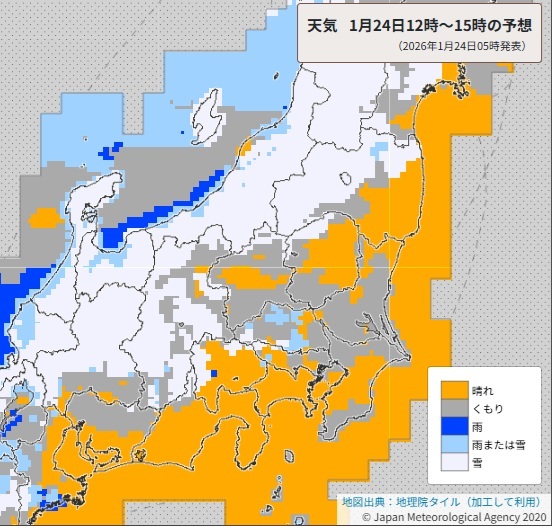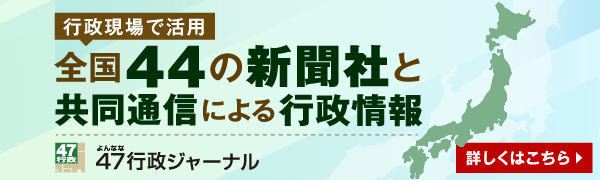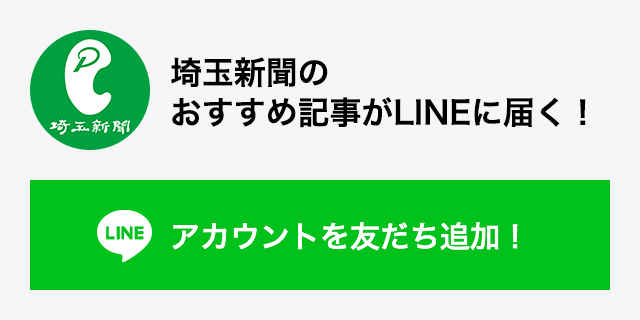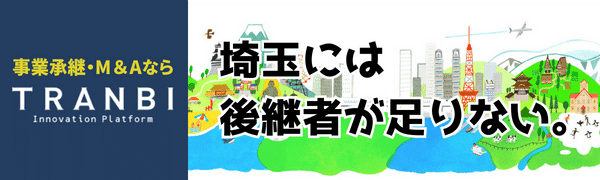パレスチナ・ガザ地区、イスラエルの大規模な地上作戦続く…パレスチナにルーツ持つ日高の男性、飯能で平和訴えデモ
パレスチナ・ガザ地区で、武装組織ハマスの掃討を掲げるイスラエルの大規模な地上作戦が続いている。一方、アカデミー賞受賞映画の舞台となったヨルダン川西岸地区でも、軍や武装した入植者によるパレスチナ人住民への排除や襲撃が後を絶たない。1948年5月のイスラエル建国に伴う「ナクバ(大惨事)」で祖父母が祖国のパレスチナを追われたサーメル・アブアルハイジャさん(36)=日高市=は、「私の故郷は占領された。戻れるなら戻りたい」と思いを打ち明けた。
■苦難続くガザ 「人ごと」と思わないで
アブアルハイジャさんは2016年に来日。現在は飯能市の「アラブカフェ」で本場の中東料理を振る舞う。「祖父は父が生まれる数日前に亡くなった。占領下のパレスチナに戻った後、二度と家族の元に戻れなかった」。ナクバ後は国境警備が厳重ではなく、行き来が可能だった。祖父が家に向かい、イスラエル軍に殺害されたと考えているという。
23年10月のハマスによるイスラエル攻撃以来、ガザ地区での死者数は5万人を超える。今年3月には停戦合意が破綻し、支援物資も5月19日まで止められたため、人道危機の深刻化が懸念される。
3月下旬、イスラム教のラマダン(断食月)のイベントをカフェで開いたアブアルハイジャさんは料理とともに、戦禍の市民への思いを込めた曲を披露。アブアルハイジャさんらと飯能駅でスタンディングデモを行っている元中学校教諭の小俣洋一郎さん(76)は「中東の原油に依存する日本人も自分事として考えるべきだ」と話し、市民の悲しみや恐怖を奏でる弦楽器の音色に聴き入った。
難民キャンプで生まれ、県内で暮らす30代のパレスチナ人男性は「祖父はナクバの際、両親を目の前で殺され、家を奪われ、人間が住む環境とは程遠い生活を強いられた」と明かす。10代の頃、避難先の国でもイスラエルによる侵攻に直面し、「人々が自分の子どもの遺体をビニール袋に集めるのを手伝った。人が死んでいくのを見ても、何もできなかった」。パレスチナ暫定自治政府も、停戦を求めるデモ活動にも期待はないと背を向けるが、「子どもの殺害だけは、もうやめてほしい」と悲痛な思いを訴えた。
だが、アブアルハイジャさんは市民の力を信じ、週末、駅前に立ち続けている。「『デモでは何も変わらない』とは思わない。変化のきっかけになるはず」と話し、「パレスチナはナクバを経ても戦い続けているが、中東で受け入れられていないイスラエルは長くは続かない」と力を込めた。妻の小林由佳さん(43)は「最初は夫が子どもにガザの現地ニュースを見せるのに抵抗があったが、今はパレスチナにルーツを持つわが子にとって知るべきことだと思う」と話す。「何百人殺されても日本のニュースでは5分も流れないが、現地の人々も子どものために将来の平和を願っているのは私たちと同じ。多くの人に人ごとじゃないと知ってほしい」と語った。
■「日本への情報不十分」 東京外大名誉教授・藤田さん
攻撃の停止を求める動きは西側諸国からも出始めているが、解決の糸口は見えない。中東問題に詳しい東京外語大学名誉教授の藤田進氏は「国際人権法に違反する暴虐が行われていることは事実。米国に追従する日本政府にも責任があり、国民は『人を殺すな』と言い続けなければ」と話す。
藤田氏によると「停戦中も(パレスチナ人の)人質解放の際などに嫌がらせや攻撃が行われ、完全な停戦ではなかった」。日本メディアの報道については「情報が少なく、米国寄りの見方が中心」と十分に伝わっていないことを懸念し「アラビア語の『アルジャジーラ・ネット』や米国の『パレスチナ・クロニクル』は現地の情報を詳しく伝えている」と視野を広げる重要性を強調した。
停戦協議に乗り出し、進展を見せていないトランプ米大統領については「パレスチナに開発の論理を持ち込み、極めていいかげん」と指摘。中東の産油国から西側諸国への石油パイプラインやタンカー航路を確保するため、米国がイスラエル建国や軍事拠点としての発展を助けた歴史的経緯を説明し、「米国は国際平和への責任を投げ出すべきではない」とした。
一方で、戦争を支持しないイスラエル国民の国外流出や、各国でユダヤ人の若者が中心となって停戦を求める活動も起きている。日本でも「現地で支援活動をしてきた人の発信が評価され、市民の認識が広がりつつある」と言う。市民の動きは状況を変えるまでには至っておらず、「虐殺する側のシナリオが変わらない限り、パレスチナの苦難は続くだろう」と見通しは厳しい。それでも、「パレスチナ人は希望を諦めない。生きるため協力し合う市民には大きな力がある」と見つめ続けている。