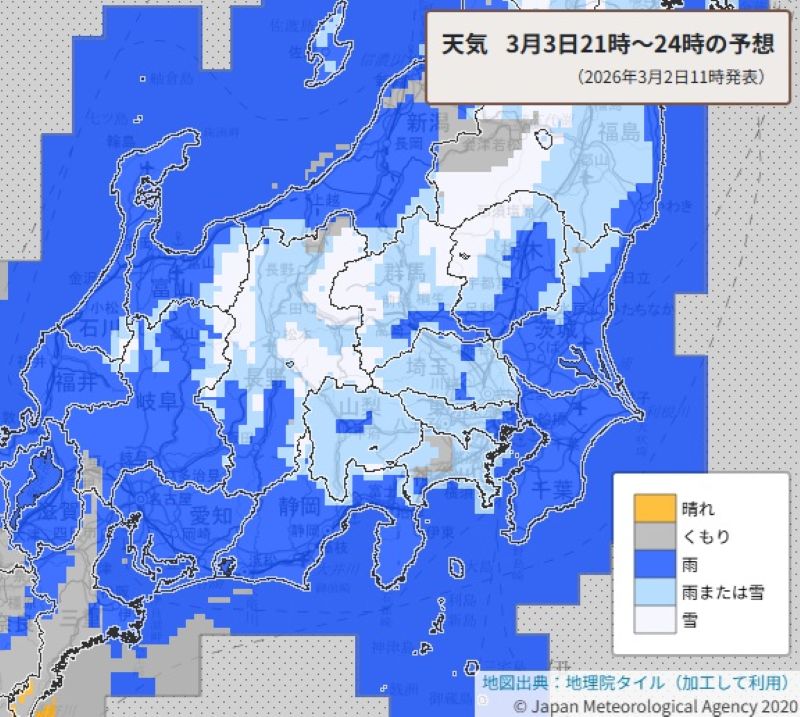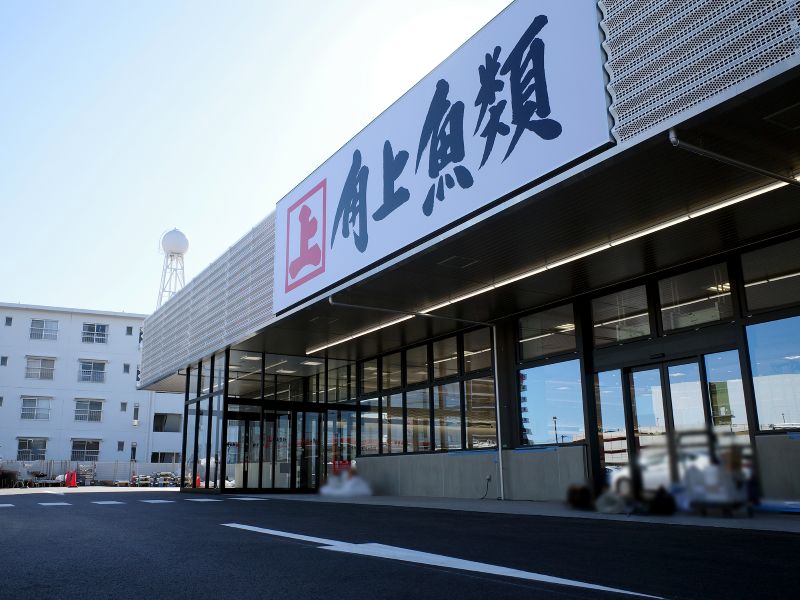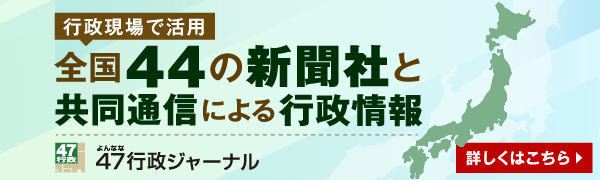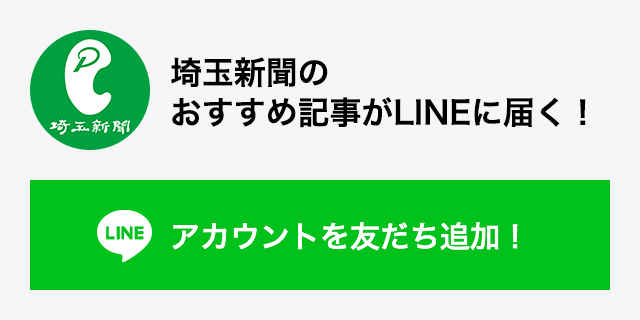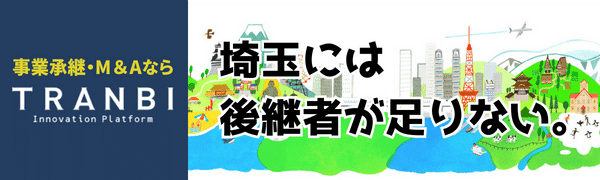自殺も考えた男性、奴隷扱いされ夜逃げ…困窮の闇 NPOに救われ、生活保護から卒業「SOSの現場見て」
生活困窮者を支援しているNPO法人「ほっとプラス」(さいたま市見沼区)で、小原秀之さん(47)は今年3月から生活相談員を務めている。長期化するコロナ禍で、失業や家賃を払えないとの相談が増加しているという。小原さんは自身の体験に重ねながら、「政治は困っている人に目を向けてほしい」と訴えた。
東京都台東区の出身。中学卒業後におじの経営する都内の飲食店で働いた。週1回1万円程度の小遣いを受け取る程度で、20歳ごろからはパチンコ店で働き始める。おじは実家を担保に数千万円の借金を重ね、32歳のときに実家は売却された。一緒に暮らしていた父親、祖母と離れ、派遣社員として、長野県飯田市内の工場に勤務。2008年のリーマンショックのあおりを受けて、派遣切りに遭う。
住まいを失った小原さんは、ネットカフェ生活を余儀なくされ、不安から気持ちが沈み眠れない日が続く。生活保護を受給して生活を立て直したものの、コンビニエンスストアの夜勤や派遣の仕事にしか就けない。勧誘されて勤務した飲食店では、月400時間働いたこともあったが、タイムカードを月160時間以上押すなと迫られた。「奴隷のように働かされる」と、オーナー所有のアパートから夜逃げした。
糖尿病の持病があり、仕事を探そうとしても事前の健康診断で落とされる。所持金が底をついた18年12月、相談した都内の区役所のケースワーカーから、県東部の無料低額宿泊所を紹介された。2畳ほどの部屋に貧相な食事、門限も決められていた。家賃、光熱費、食費として、生活保護費のうち約10万円を支払うと、残るのは1万数千円。施設長に就業を相談したら「生活保護を受けないなら出ていってもらう」と言われ逃げた。
「上を向いて歩けずに下を向いてばかりいた。選択肢が見えない。残された道は路上生活をするか、自殺か」と自問自答した。社会とつながっていたいと、携帯電話の料金だけは支払い続けていた。19年3月、「貧困」「シェルター」と検索して、「ほっとプラス」がヒットした。
電話をかけて、6畳間のシェルターに入居することができた。支援を受けてさいたま市で生活保護を申請した。「年齢的に最後のチャンスかもしれない。もう一度やり直したい」。見沼区でアパートを借り、コンビニの夜勤をしながら、生活保護を抜け出した。
昼の仕事に就こうと、ほっとプラス代表理事の平田真基さん(34)に相談し、生活相談員に誘われた。小原さんはこの間、夜回り活動や炊き出しボランティアに参加していた。平田さんは「困っている人を助けようと行動する小原さんを見て、一緒に活動できたらと思った」と話す。小原さんは「自分は命を救われ、人生の立て直しをさせてもらった。一人でも救うことができれば」と活動している。
コロナの影響から仕事を失って同時に住まいをなくした人、所持金が数百円しかない人、電気やガスを止められた人、保険証を持てずにぜんそくの持病がある人。東京五輪後に働く場を失った人。ストレスの増加によるメンタルの不調を訴える人も多いという。
生活保護へのバッシングが以前に起きた。「家賃、光熱費、携帯電話代を支払えば、残るのは約6万円。ぜいたくと言われるが、保護費で生活するつらさを分かっていない」。厚生労働省はコロナ禍で「生活保護の申請は国民の権利です」と呼び掛けているが、小原さんは「役所はまだ昔のまま。支援者が同行しないと、『まだ働ける』と追い返されるケースもある」と批判する。
相談電話を受けると、小原さんは生活保護の受給時に持てなかった自身のバイクで駆け付ける。食料や水の支援物資を携えて急ぐ。「SOSを出している人の気持ちはよく分かる。住む場所を失い、心も体も弱っている。路上生活者ら苦しんでいる人は後回しとしか思えない。政治家は現場を見てほしい」