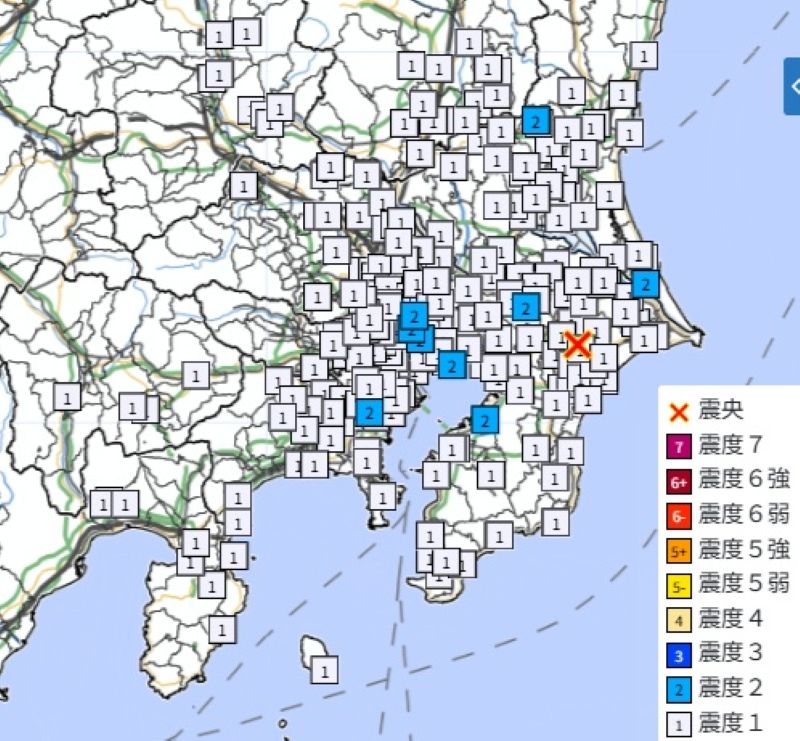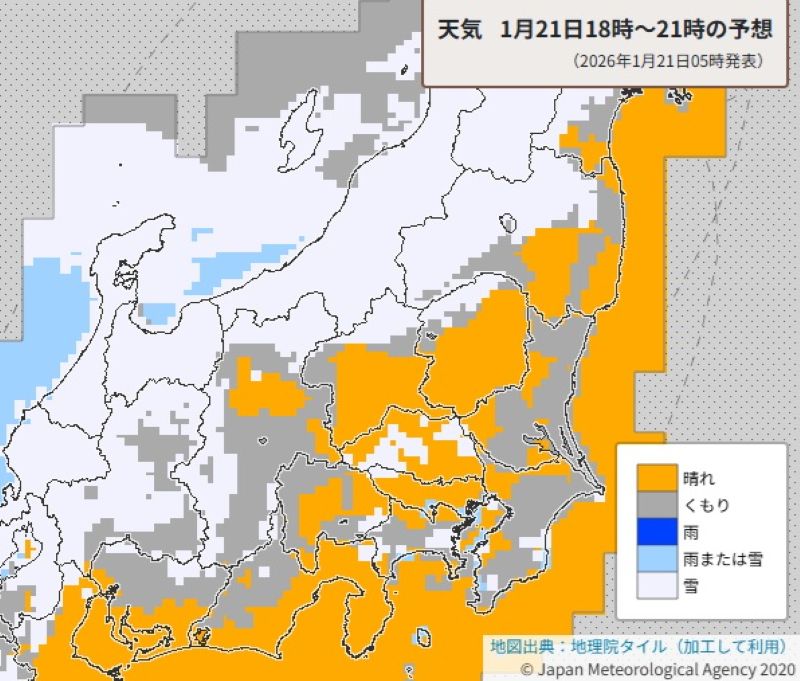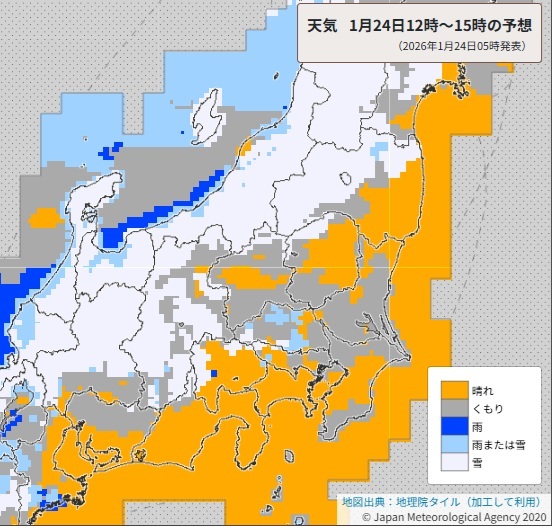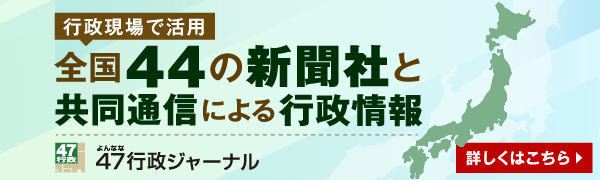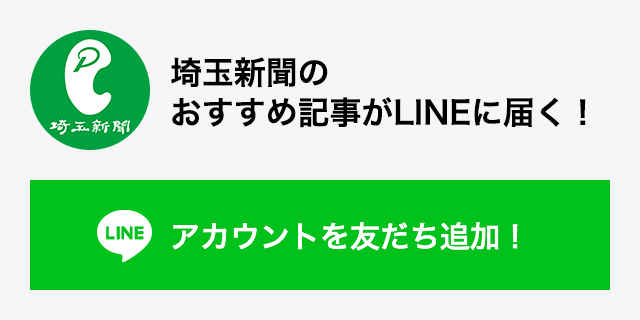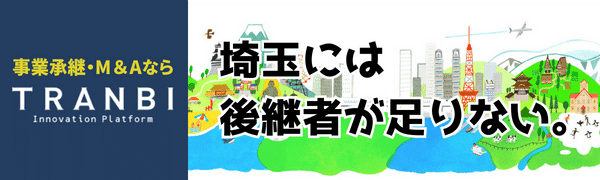“のんびり屋”3年目に頭角…埼玉のイチゴ「あまりん」 開発に8年、1日5kg食べた日も こだわりと誇り結実
埼玉県春日部市の観光農園「ヒロファーム」は、日本野菜ソムリエ協会主催「第1回全国いちご選手権」(2023年)で、県産品種のイチゴ「あまりん」で最高金賞に輝いた。
暖かな日差しの1月下旬、あまりん約5千株を栽培するヒロファームのハウス。受粉のため、マルハナバチが飛び回る。つやつやした赤い果実を頬張ると、ジューシーで強い甘さと、かすかな酸味。まさに至福の味わいだ。
県によると、2022年産の県内のイチゴ栽培面積は95ヘクタールで全国17位。産出額は同12位(45億円)で、全国1位の栃木県(277億円)の2割にも満たない。
それでも、埼玉イチゴの快進撃が止まらない。今年2月に開催された第2回全国いちご選手権でも、秩父市の生産者が出品したあまりんが最高金賞。ヒロファームに続いて、埼玉イチゴが連覇を果たした。昨年の同選手権では、県内からエントリーした6品全てが入賞したことから、日本野菜ソムリエ協会から全国初の「プレミアムいちご県」にも認定されている。
原動力となったのは、18年から本格栽培されている「あまりん」「かおりん」だ。県と契約を結んだ県内の農家だけが生産できる。味は良いが、収穫量は多収量の品種と比べると3分の2程度しかない。開発した県農業技術研究センターの尾田秀樹(51)は「他県だと広まらなかったと思う。味にこだわる農家が多い埼玉だからこそ。味を追求するプライドを感じる」と語る。
「あまりんはポテンシャルが高い。だから特別なことをせず、イチゴにとって最適な環境をつくるだけでいい」。ヒロファームの社長、中村知由(ともよし)(40)は強調する。
農業用資材販売会社の実践モデルとして17年に開業したヒロファーム。中村が取り組むのは、データを活用した次世代農業だ。
20~30品種を栽培しているハウス6棟(計50アール)の内部にセンサーを設置し、温度、湿度、日照量などを24時間体制で測定。甘みを増す光合成を促進するため、炭酸ガス供給のタイミングなどもコントロールしている。「イチゴは品種によって個性がある。あまりんは『のんびり屋』で、すぐに言うことを聞いてくれない。データを活用しながら試行錯誤している」
あまりん人気で新規参入が増える中、質の維持も課題という。「ファンを裏切らないよう、いいものを作り続けることが大事。本当に優れたイチゴなので大切にして、埼玉の農家皆で盛り上げたい」
■味にこだわり開発8年
「あまりん」「かおりん」を開発したのは、県農業技術研究センターの尾田だ。観光農園向けに「味の良さ」にこだわり、あまりんは2009年から8年、かおりんは08年から9年がかりで生み出された。
あまりんは「ふくはる香」と「やよいひめ」の掛け合わせ。そこに至るまで、さまざまな品種を交配し、試食して候補を絞る作業を繰り返した。1日約5キロのイチゴを食べることもあったという。
並行して開発されたかおりんは、開発1年目から際立った存在だった。一方、あまりんは「形と色はいいけれど…」という評価。しかし3年目の12年1月、あまりんは突然、頭角を現す。「1年目の印象がないので、落とされていてもおかしくなかった。けれど(3年目に)ずば抜けてうまくなった。なぜ急においしくなったのか、本当に不思議」
あまりんとかおりんは一部は市場に流通しているが、観光農園や農家による直売がほとんどだ。そこで3年前に市場向けの「べにたま」も育成。べにたまは昨年12月、「クリスマスいちご選手権」で最高金賞に。県はこの3品種のイチゴをPRしている。
尾田は「品種の寿命は10~15年。次を見据え、アップグレードしたイチゴを作りたい」と話している。(敬称略)