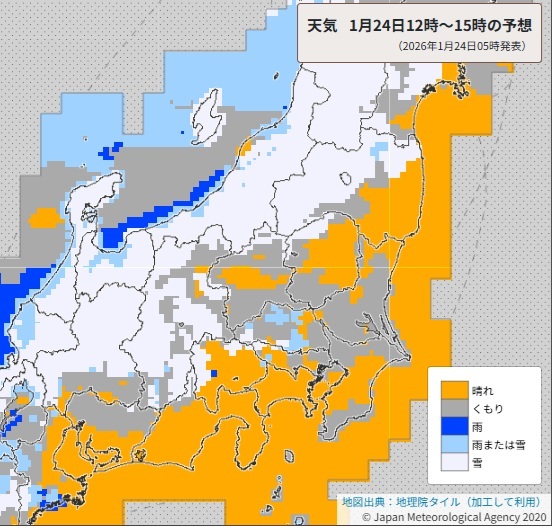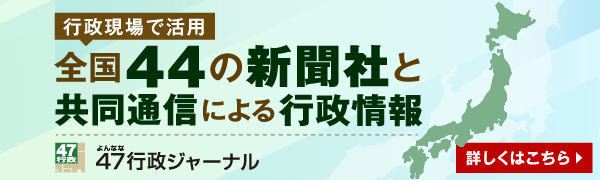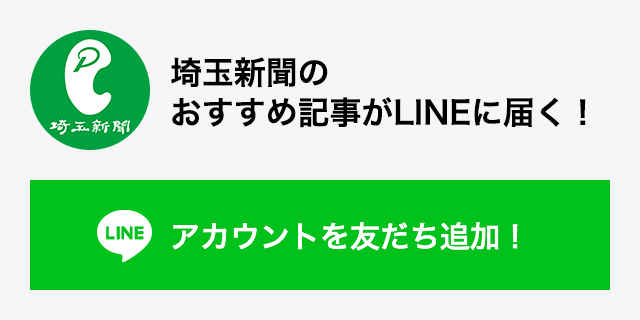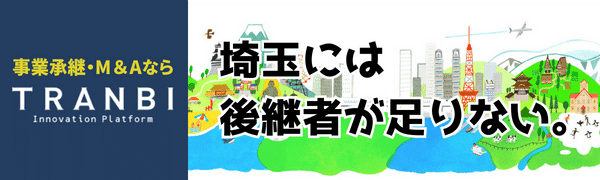「骨と皮の状態」で拾われ…日本人だと知らず育つ 戦後の混乱期に取り残された中国残留孤児 戦後世代が体験伝える 語り部を育成 現在は13人が在籍
戦後の混乱期に中国に取り残され、その後日本に永住帰国した中国残留孤児や家族らを支援する、国の宿泊型研修施設「中国帰国者定着促進センター」が、所沢市並木にあった。設立から2016年2月の閉所までの32年間で、樺太からの帰国者も含め6644人が日本語や生活習慣を学んだ。中国残留孤児たちの苦悩した体験を伝えるため、戦後世代の語り部の育成が行われている。
■究極の選択
「母の実母は、どうすれば子どもだけでも残せるか、究極の選択をしたのだと思う」。東京都練馬区で今月9日、中国残留孤児2世の長久保まりさん(52)が、母の間瀬珠美さん(81)の人生を語った。1歳だった間瀬さんは「骨と皮の状態」で拾われ、自身が日本人だと知らずに育った。17歳の時、「日本の名前や出自が書かれた紙があった」と叔父に聞いたが、養父母に真実を尋ねることはできなかった。
長久保さんは「母が取材を受けた記事には、30年以上、日本人だと言えない悩みを抱えて生きたと書かれていた。子どもに弱音を言わない強い母だった。語り部として母の人生をたどり直して初めて、母のつらい心情が強い痛みとして、私の中に流れ込んできた」と胸の内を語る。間瀬さんは養父母の死後、1991年に48歳で中国人の夫、長男、長久保さんの家族4人で永住帰国した。
■「所沢が故郷」
帰国した長久保さんらは、所沢市の中国帰国者定着促進センターで、日本語や日本の生活習慣を学んだ。長久保さんは「先生たちは優しく寄り添ってくれて、本当に大好き。とても幸せな時間だった」と目を細める。帰国者とその子どもや養父母まで、幅広い年代が集まった。生活環境もそれぞれで、識字学習を受けていない人もいた。講師は教材を一から作り、プログラムを考えたという。
帰国者数は72年の日中国交正常化を機に増加しており、入所者は設立した83年度に86人、87年度には最多の642人になった。同センターで日本語を教えた馬場尚子さん(68)は「入所者同士でも異文化交流。多様性のるつぼだった」と当時の状況を振り返る。「『所沢が故郷のようだ』と言う方も多い。一日中机に座って、(入所期間の)6カ月間で住む場所も決めなければならず、大変だったと思う」と話す。
■一人の人生を考える
同センターは帰国者の減少に伴い閉所となり、最終年度の入所は3人だった。役割を引き継いだ、「中国帰国者支援・交流センター」(東京都台東区)は、中国残留邦人らの体験を後世に残そうと、2016年度から語り部育成事業を開始した。担当者は「語り部は、その人がなぜ中国に渡ったのか、向こうでの体験、帰国の経緯、日本に帰ってからの人生について語る。一人の人生を知ってもらうことで、戦争や平和を考えるきっかけになればと思う」と願いを込める。
在籍する語り部は現在、センターで3年間の研修を受けた30~70代の13人。戦後に生まれた世代が、残留邦人やその親族らから聞き取った内容を語り継いでいる。長久保さんは「残留孤児として確認されている2818人のうち、母も含めて1534人の身元が分かっていない。過去の問題でなく今も続いていること。これからも伝えていかなければ」と強調した。